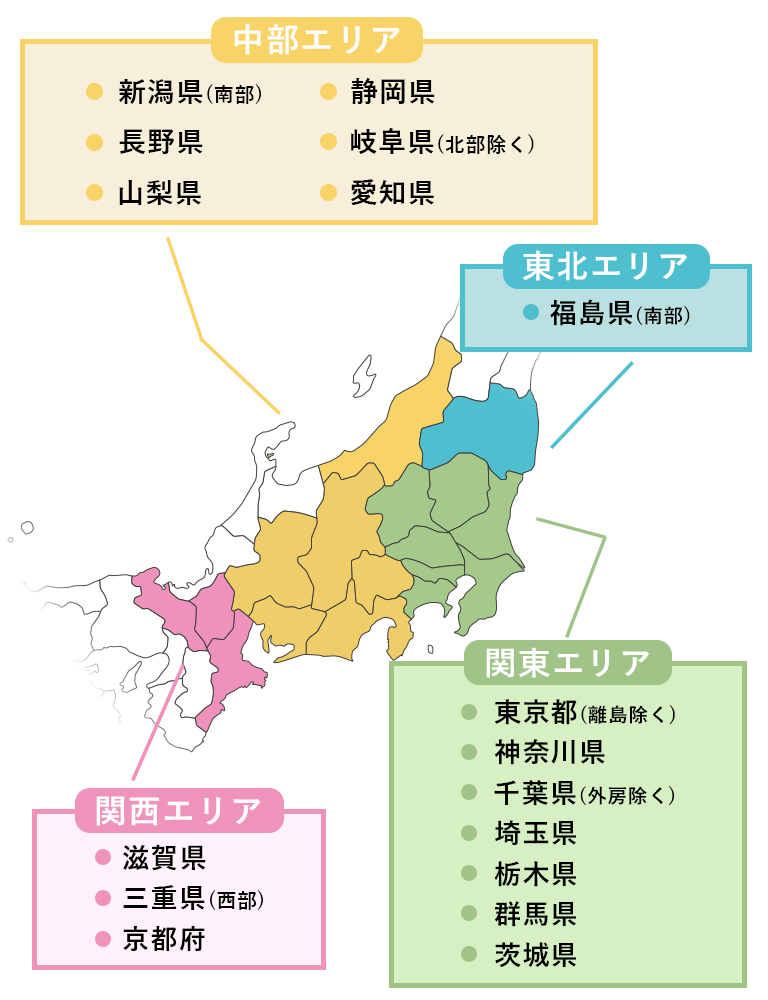選挙活動において、選挙カーを導入すべきか、その効果はどれほどあるのか、判断に迷うことはありませんか?
有権者からは「うるさい」「時代遅れ」といった厳しい意見も聞かれる一方で、多くの候補者が今なお選挙カーを活用しています。
本記事では、選挙カーが持つ効果と候補者が利用をやめない理由を、データにもとづいて深掘りします。
さらに、効果を損なわないための法律上のルールや、逆効果を避けるための騒音対策、効果を最大化する方法もまとめました。
ぜひ選挙戦略を立てるうえでの参考にしてください。
選挙カーはどれくらい効果がある?
選挙カーの効果については賛否両論があり、とくに都市部では騒音として捉えられることが多くなっています。
一方で、選挙カーには投票行動を変える力があることも研究で分かりました。
ここでは、以下の3つの観点から選挙カーの効果を解説します。
- ・時代遅れで逆効果という意見
- ・候補者自身も効果に疑問を抱いている現実
- ・それでも候補者が選挙カーをやめない4つの理由
それぞれ見ていきましょう。
時代遅れで逆効果という意見
選挙カーに対して、有権者からは厳しい意見が数多く寄せられています。
読売新聞と早稲田大が行った郵送全国世論調査では、選挙の際に参考にした情報源として「選挙カーでの呼びかけ」をあげた人はわずか6%。
これは、調査項目の中でもっとも低い結果でした。
具体的な批判として、子供の昼寝や夜勤明けの睡眠を妨げる「騒音問題」がもっとも深刻です。
そのほか、低速走行による「交通渋滞」や、アイドリングによる「環境負荷」なども指摘されています。
候補者自身も効果に疑問を抱いている現実
実は、選挙カーの効果に疑問を持っているのは有権者だけではありません。
福島大学の調査によると、多くの候補者が選挙カーの目的を「氏名や政策の周知」と回答しています。
しかし、実際に感じた効果は「有権者とのコミュニケーションがとれた」「選挙ムードが盛り上がった」など、目的とは異なる声が少なくありませんでした。
このことは、候補者が意図する直接的な効果と、実際に得られる効果との間にズレがあることを示唆しています。
目的と効果が必ずしも一致しないため、多くの候補者は「効果があるかどうか分からないが、やらないわけにはいかない」という複雑な心境を抱えています。
それでも候補者が選挙カーをやめない4つの理由
有権者から批判があり、候補者自身も効果を疑問視しているにもかかわらず、なぜ選挙カーはなくならないのでしょうか。
ここでは、候補者が選挙カーの利用をやめない4つの理由を掘り下げます。
- ・効果が実証されているから
- ・ほかの候補者がやっているから
- ・ほかに有効な手段がないから
- ・支持者からの要望があるから
詳しく見ていきましょう。
効果が実証されているから
関西学院大学の研究では、選挙カーが通過した地域の住民は、通過しなかった地域と比較して約2倍の確率でその候補者に投票する傾向があることが実証されています。
この効果は「単純接触効果」と呼ばれる心理現象によるもので、繰り返し名前を聞くことで無意識のうちに親近感が生まれるというメカニズムです。
好感度は上がらなくても、投票行動には影響を与えるという特異な現象が確認されています。
とくに政治への関心が低い不動票層に対しては、選挙カーによる名前の刷り込みが投票先決定の重要な要因となることがあります。
ほかの候補者がやっているから
選挙は相対的な競争であり、自分だけが選挙カーを使わないことは大きな不利になる可能性があります。
福島大学の調査では「効果の有無にかかわらず、誰かがやれば全員がやる。やらなければ落選候補」という回答が複数見られました。
このような横並び意識や競争環境が、効果への疑問がありながらも選挙カーの使用を継続させる一因となっています。
選挙カーを使わないことが、有権者に特定の印象を与える可能性もあります。
競合候補が選挙カーで積極的に活動している中、自分だけが静かな選挙を展開することは、存在感の低下につながりかねません。
ほかに有効な手段がないから
公職選挙法では戸別訪問が禁止されており、不特定多数の有権者に直接アプローチできる手段が限られています。
選挙カーは、法的に認められた数少ない能動的な選挙活動の1つであり、代替手段が存在しないという構造的な問題があります。
インターネットを使った選挙運動は解禁されましたが、高齢者層への訴求力は依然として限定的です。
街頭演説は効果的ですが、移動範囲が限られるため、広い選挙区全体をカバーすることは困難です。
このような制約の中で、選挙カーは依然として貴重な選挙ツールと位置づけられています。
支持者からの要望があるから
後援会や支持者から「もっと選挙カーで回ってほしい」という要望が寄せられることも、選挙カーを継続する大きな理由の1つです。
とくに地方では、選挙カーが来ることで選挙の盛り上がりを実感し、候補者の熱意を感じるという支持者が多く存在します。
選挙カーは単なる宣伝手段ではなく、支持者との絆を確認し、士気を高める役割も果たしています。
後援会の活動拠点を回ることで、支持者の結束を強め、選挙活動全体の活性化につながるでしょう。
選挙カーの効果を損なわないための4つのルール
選挙カーを効果的に活用するためには、公職選挙法で定められたルールを正確に理解し、遵守することが不可欠です。
ルール違反は法的な処罰だけでなく、有権者からの信頼失墜にもつながりかねません。
ここでは、以下4つを説明します。
- ・活動が許可される時間帯
- ・音量規制と注意すべき場所
- ・走行中の演説と連呼行為の違い
- ・選挙カーに乗る人の規定と腕章
これらのルールを守ることで、効果的かつ適法な選挙活動が可能になります。
▼選挙運動のルールについて詳しく知りたい方はこちら
選挙運動のルールとは?告示前にできることややってはいけないことも解説
活動が許可される時間帯
選挙カーの拡声器を使用して音を出せる時間は、法律で厳格に定められています。
具体的には、選挙の公示・告示日から投票日の前日までの期間中、「午前8時から午後8時まで」の12時間に限られます。
この時間帯を過ぎてマイクを使用する行為は、公職選挙法違反となるため徹底した時間管理が必要です。
選挙運動自体は投票日前日の24時まで可能です(ただし拡声機を使用しない活動に限る)。
しかし、音を出す活動にはこの時間制限が課せられていることを忘れてはいけません。
陣営全体で時間を常に意識し、ルールを遵守する姿勢が求められます。
音量規制と注意すべき場所
選挙カーの音量について、具体的なデシベル単位での規制は公職選挙法にはありません。
しかし、法律では「学校や病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない」と規定されています。
これは罰則のない「努力義務」ですが、候補者の社会的な配慮や倫理観が問われるポイントです。
これらの施設周辺を通過する際は、マイクの音量を大幅に下げる、あるいは一時的にオフにするといった行動が求められます。
候補者としての信頼を築くためにも、細やかな配慮が不可欠です。
▼選挙カーの許可・音量規制・対応策について詳しく知りたい方はこちら
選挙カーで音楽を流すのは違法?許可・音量規制・対応策を解説
走行中の演説と連呼行為の違い
走行中の選挙カーから音声で訴えかける活動は、候補者の氏名や政党名などを繰り返し訴える「連呼行為」のみが許可されています。
一方で、具体的な政策や公約を訴える「演説」は、必ず車を完全に停止させた状態で行わなければなりません。
走行中に演説することは「流し演説」として公職選挙法で禁止されています。
車を停止させて演説を行う際は、「街頭演説用標旗」を掲げ、交通の妨げにならないよう配慮することが必要です。
演説と連呼行為の違いを明確に理解し、使い分けることが重要です。
選挙カーに乗る人の規定と腕章
マイクを握ってアナウンスなどを行うスタッフは「車上運動員」と呼ばれ、選挙管理委員会から交付される規定の腕章を必ず着用しなければなりません。
車を停止させて街頭演説を行う際には、同じく選挙管理委員会から交付される「街頭演説用標旗」を、車の外から見えるように掲示する必要があります。
これらの腕章や標旗、そして車体に取り付ける表示板などが1つでも欠けていると、その状態での活動は公職選挙法違反と見なされます。
交付された表示物は紛失しないよう厳重に管理し、活動中は規定どおりに必ず掲示・着用してください。
選挙カーはうるさい?逆効果にならないための対策
選挙カーを運用するうえで避けて通れないのが「騒音」に関する苦情です。
どれだけルールを守っていても、有権者の生活に影響を与える以上、一定数のクレームは避けられません。
しかし、事前の対策と配慮によって、その数を最小限に抑え、逆効果になるのを防ぐことは可能です。
ここでは、有権者との無用な摩擦を避けるための騒音対策を紹介します。
- ・立候補者の84.6%が騒音対策の工夫を実施している
- ・特定施設周辺で音量を下げるか停止する
- ・地域特性に合わせて運動時間を調整する
- ・効率と騒音配慮のバランスを取る
これらの対策は、候補者の危機管理能力と有権者への配慮を示す絶好の機会にもなります。
立候補者の84.6%が騒音対策の工夫を実施している
選挙カーの騒音問題は有権者だけでなく、候補者にとっても重大な課題として認識されています。
福島大学の調査が立候補者を対象に行った調査では、実に84.6%もの候補者が、有効な選挙運動にするために何らかの工夫をしていると回答しました。
工夫の内容としてもっとも多かったのが、騒音への配慮でした。
このデータは、多くの候補者が有権者の生活環境に気を配りながら活動しようと努めていることを示しています。
特定施設周辺で音量を下げるか停止する
騒音対策としてもっとも基本的なのが、特定の施設周辺での配慮です。
公職選挙法でも努力義務が定められている学校や病院はもちろん、図書館や斎場などの前を通過する際には、とくに細やかな気配りが求められます。
具体的な対策として、マイクの音量を普段より大幅に下げる、あるいは音楽やアナウンスを一時的に完全に停止するといった行動などです。
こうした配慮はその場にいる人々だけでなく、その様子を見ているほかの有権者に対しても、候補者の思慮深い人柄をアピールすることにつながります。
▼選挙カーのスピーカーで有権者に好印象を与える方法について詳しく知りたい方はこちら
選挙カーのスピーカーは音量より「質」!有権者に好印象を与える活用方法も紹介
地域特性に合わせて運動時間を調整する
画一的な運動計画ではなく、地域の特性や住民の生活リズムに合わせた活動を行うことも、効果的な騒音対策の1つです。
たとえば、候補者からは騒音問題として「住宅地で赤ちゃんが目を覚ましたと通知された」という経験も報告されています。
子育て世帯が多い住宅街では、時間帯によって音量を調整するなどの配慮が考えられます。
夜勤明けの方が就寝している可能性がある地域では、活動開始直後の午前中の大音量での活動は避けるべきでしょう。
このように、地図や地域の情報からライフスタイルを想像し、時間帯によって音量や活動内容を調整することで、無用な反感を買うリスクを減らせます。
効率と騒音配慮のバランスを取る
選挙運動では、限られた時間でいかに多くの有権者に声を届けるかという「効率」が求められます。
しかし、この効率を過度に追求すると、騒音問題を引き起こす原因となりかねません。
たとえば、高台の集合住宅から広範囲にアナウンスをすれば効率はよいかもしれませんが、意図せず広範囲に騒音をまき散らしてしまう可能性も。
大切なのは、運動の効率と騒音への配慮のバランスを取ることです。
この2つの視点を常に持ちながら活動計画を立てることが、最終的に有権者からの理解を得ることにつながります。
選挙カーの効果を最大化するための方法4選
選挙カーは、ただ走らせるだけではその効果を十分に発揮できません。
ルールを守り、騒音に配慮することはもちろんですが、さらに一歩進んで有権者の心に響く戦略的な活用が求められます。
ここでは、選挙カーの効果を最大化するための方法を紹介します。
- ・最適な車種を選び看板を工夫する
- ・候補者自身がマイクを持って直接訴える
- ・有権者に届く運行ルートを計画する
- ・ウグイス嬢の声質や話し方を工夫する
それぞれ見ていきましょう。
最適な車種を選び看板を工夫する
選挙カーの効果はその見た目、つまり車種と看板のデザインに大きく左右されます。
車種選びでもっとも大切なのは、選挙区の道路事情です。
狭い路地や古い住宅街の奥まで声を届けたい場合は、小回りの利く軽自動車やコンパクトカーが有効です。
一方で、幹線道路沿いでの活動が中心なら、大きな看板を設置できるワンボックスタイプが視認性を高めます。
看板デザインの鉄則は、候補者の「顔」と「名前」をできるだけ大きく、明確に配置することです。
また、夜20時まで活動することを考え、看板を照らす照明の設置も忘れてはいけません。
候補者自身がマイクを持って直接訴える
選挙カーから候補者自身が直接語りかけることは、有権者との距離を縮めるもっとも効果的な方法の1つです。
ウグイス嬢任せにせず、候補者が助手席から身を乗り出して挨拶することで、熱意と誠意が伝わりやすくなります。
とくに、信号待ちなどの短い停車時間は絶好のアピールチャンスです。
たとえば「〇〇町の皆様、候補者の〇〇です!この交差点をお借りして一言ご挨拶申し上げます」などがあげられます。
自分の声で語りかけることで、有権者に強い印象と親近感を与えられます。
短い時間でも、候補者本人が積極的に前に出る姿勢を見せることが、信頼獲得につながるでしょう。
有権者に届く運行ルートを計画する
より多くの有権者に接触するため、毎日同じ道・同じ時間帯に通ることを避け、計画的に選挙区内をくまなく走行することが肝心です。
地図の航空写真などを活用して、住宅が密集しているエリアや団地を事前に特定し、そこを重点的に回る計画を立てることも効果的です。
右折を避けて左回りのルートを基本とすることで、時間のロスを最小限に抑えられます。
時間帯によってターゲット層を意識し、日中は商店街、朝夕は駅前など、戦略的なルート設定を心がけましょう。
ウグイス嬢の声質や話し方を工夫する
ウグイス嬢のアナウンスは、選挙カーの印象を決定づける要素です。
効果的なアナウンスのコツは、走行速度に合わせて、長文ではなく短いフレーズをテンポよく繰り返すことです。
また、アナウンスの冒頭に「〇〇町の皆様、こんにちは」と具体的な地域名を入れるだけで、住民の注意を引きつけ親近感を持たせられます。
さらに大切なのが、沿道で手を振ってくれる人を見つけたら、即座に「温かいご声援、ありがとうございます」と反応することです。
この双方向のやりとりが、一方的な宣伝ではないという雰囲気を作り出し、有権者の心を掴みます。
まとめ:選挙カーの効果を理解して最適な選挙戦略を選択する
選挙カーの効果を最大限に活用するためには、専門的な設備とノウハウが不可欠です。
W1N選挙カーでは、選挙活動に必要なすべての装備がコミコミで7日間87000円から提供しています。
高音質マイクやLED照明などの最新設備に加え、印刷会社としてのデザイン力を生かした看板製作で、有権者への訴求力を高めます。
さらに掲示板やポスターとの同時発注で最大10万円の値引きも可能です。
書類作成や申請手続きのサポート、簡単な看板着脱システムなど、候補者の負担を軽減するサービスも充実しています。
選挙カーレンタルから印刷物まで、ワンストップでの選挙活動支援をぜひご検討ください。

浅田 孝
アサダ印刷株式会社 代表取締役
W1N選挙カー 代表
1968年生まれ
累計400を超える選挙活動に従事、選挙カー貸出とともに候補者の寄り添い、共に当選を目指す。
モットーは、問い合わせメールに最短で返信(休日関係なく)依頼事は、経験なくても断らず全力で対応する。
常に、候補者目線で考え行動する。
選挙のプロであり、印刷のプロ。