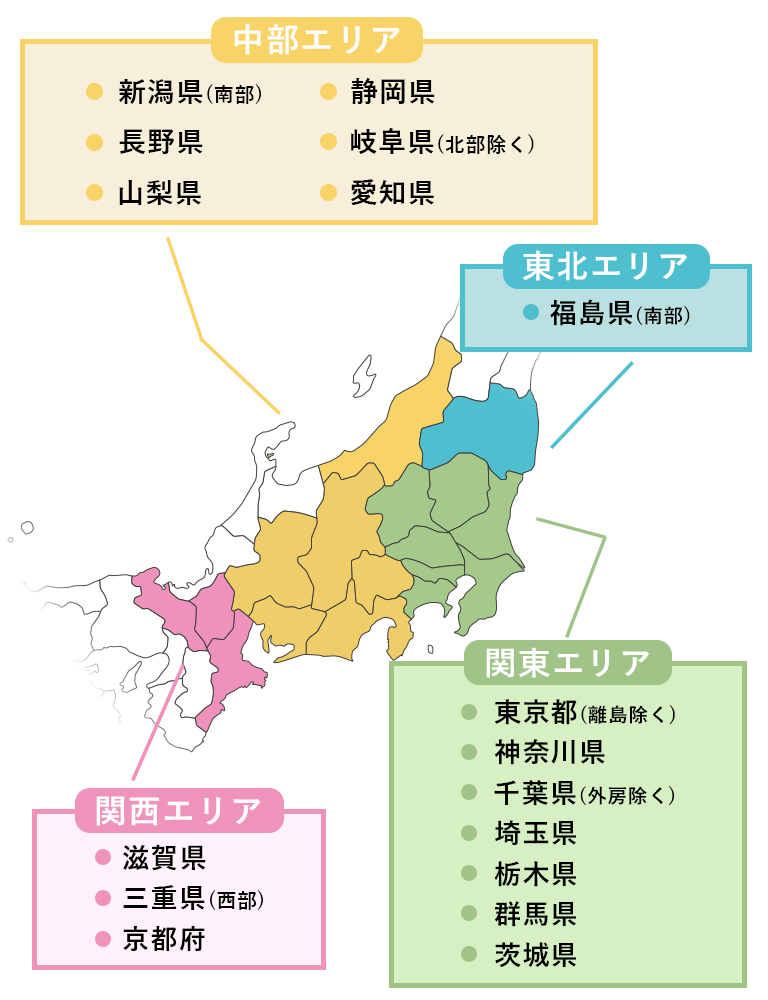選挙への出馬を検討する際、選挙カーをはじめとする多額の費用が必要です。
しかし、選挙運動にかかる費用の一部は、公費で負担される制度があることをご存知でしょうか。
本記事では、選挙カーのレンタル費用などを公費で賄うための「公費対応プラン」について、仕組みから手続き、業者選びのポイントを解説します。
クリーンで力強い選挙戦のために、参考としてください。
選挙カーの公費対応プランとは?
選挙カーの公費対応プランとは、候補者の選挙運動にかかる費用の一部を税金で賄う「選挙公営制度」を活用したサービスのことです。
ここでは、公費対応プランを理解するうえで土台となる、以下3つの基本事項を解説します。
- 契約の前に公費負担の仕組みを理解する
- 適用される選挙の種類を確認する
- 供託金が没収されると請求できない
これらの知識はプランを賢く活用し、予期せぬ自己負担を防ぐために大切です。
契約の前に公費負担の仕組みを理解する
選挙カーの費用を公費で賄える根拠は「選挙公営制度」という仕組みです。
この制度は、資産の多少にかかわらず誰もが立候補でき、候補者間で選挙運動の機会が均等に保たれることを目的としています。
そのため、国や地方公共団体が選挙運動費用の一部を負担してくれるというものです。
重要なのは、その支払い方法です。
公費は候補者に直接支払われるのではなく、候補者と契約した業者に対して、自治体から直接支払われます。
したがって、候補者が費用を立て替える必要はありません。
適用される選挙の種類を確認する
選挙公営制度は、すべての選挙で一律に適用されるわけではありません。
現在では、国政選挙や都道府県知事選挙・市区町村長選挙、そして都道府県議会議員選挙や市区町村議会議員選挙など、多くの選挙でこの制度を利用できます。
ただし、公費負担の対象となる費用の種類や限度額は、選挙の種類や自治体の条例によって異なる場合があります。
そのため、立候補を予定している選挙が公費負担の対象か、どのような内容が適用されるのかを、必ず管轄の選挙管理委員会に確認することが賢明です。
供託金が没収されると請求できない
公費負担制度を利用するには、必ずクリアしなければならない条件があります。
それは、選挙で一定以上の得票数を得ることです。
この基準となる得票数を「供託物没収点」と呼びます。
もし得票数がこの没収点を下回った場合、立候補時に法務局へ預けた供託金が没収されるだけでなく、公費負担を受ける権利も失ってしまいます。
その結果、選挙カーのレンタル費用などは全額自己負担となるため、注意が必要です。
供託物没収点は選挙の種類によって計算方法が異なりますが、たとえば市区議会議員選挙では「有効投票総数÷議員定数×10分の1」が一般的です。
当選を目指すだけでなく、この没収点を確実に上回る得票戦略が資金計画上も欠かせません。
▼選挙カーの公費負担制度について詳しく知りたい方はこちら
選挙カーの公費負担制度とは?運転手の日当とルールについても解説
選挙カー関連で公費負担の対象になる費用
選挙カーの運用にはさまざまな費用がかかりますが、そのすべてが公費負担の対象となるわけではありません。
ここでは、選挙カー関連で公費負担の対象となるおもな費用を3つ紹介します。
|
費用項目 |
公費負担の対象 |
1日あたりの上限額(例) |
|
自動車のレンタル費用 |
選挙運動で使用する自動車本体のレンタル費用(候補者1人につき1台まで) |
16,100円 |
|
燃料費(ガソリン代) |
選挙カー1台分のガソリン代(選挙運動期間中に給油したもの) |
7,700円 |
|
運転手の雇用費用 |
選挙カーの運転手への報酬(候補者1人につき1日1人まで) |
12,500円 |
上限額は東京都知事選挙の例です。
選挙の種類や自治体によって異なるため、必ず管轄の選挙管理委員会にご確認ください。
自動車借入れ契約(レンタル)の費用
選挙運動で使用する自動車本体のレンタル費用は、公費負担の対象となります。
対象となるのは候補者1人につき1台までで、選挙運動期間中に使用した分に限られます。
多くの自治体では1日あたりの上限額が定められており、たとえば東京都知事選挙は16,100円です。
上限額の範囲内であれば、実際に業者と契約したレンタル料金が公費で支払われます。
ただし、カーナビなどのオプション料金や、看板の取り付け費用などは公費負担の対象外となることがほとんどです。
契約時には、何が基本料金に含まれ、何が対象外なのかを業者に確認することが大切です。
▼選挙カーレンタル時の故障対応について詳しく知りたい方はこちら
選挙カーレンタル時の故障対応とは?トラブルの種類や対応時の流れを解説
燃料供給の費用
選挙カーを走らせるためのガソリン代も、公費負担の対象です。
対象となるのは、選挙運動用自動車1台に供給した燃料費で、選挙運動期間中に給油したものに限られます。
1日あたりの上限額が設定されており、たとえば東京都知事選挙では7,700円です。
この上限額と、選挙期間中に実際に給油した総額を比較し、いずれか低い方の金額が公費で支払われます。
燃費の悪い車で広範囲を活動する場合、上限額を超えて自己負担が発生する可能性もあるため、日々の走行ルートを計画的に管理することが求められます。
運転手雇用の費用
選挙カーを運転する人を雇用した場合の報酬も、公費負担の対象となります。
対象となるのは、候補者1人につき1日1人までです。
報酬には1日あたりの上限額が定められており、東京都知事選挙などでは12,500円が一般的です。
この上限額を超えて報酬を支払うと、公職選挙法違反(買収)に問われる可能性があるため、厳格に遵守しなければなりません。
また、公費負担の対象となるのは、あくまで運転業務に対する報酬です。
運転手がビラ配りなどの選挙運動を行った場合、その日の報酬は公費負担の対象外となるため注意が必要です。
▼選挙カーの運転手について詳しく知りたい方はこちら
選挙カーの運転手とは?公費負担制度と日当・仕事内容を分かりやすく解説
その他選挙運動で公費負担の対象になる費用
選挙運動における公費負担は、選挙カー関連の費用だけに限りません。
ここでは、選挙カー以外で公費負担の対象となる代表的な費用2つを解説します。
- ・選挙運動用ポスターの作成費用
- ・選挙運動用ビラの作成費用
これらの費用も、上限となる単価や枚数が定められています。
選挙運動用ポスターの作成費用
街の掲示板に貼り出す選挙運動用ポスターの作成費用も、公費負担の対象です。
対象となるのは、選挙管理委員会が設置するポスター掲示場の数に応じた枚数までとなります(東京都知事選挙では、ポスター掲示場数の2倍の枚数が上限です)。
公費負担の上限額は、ポスター1枚あたりの単価と枚数の両方で定められています。
とくに単価の上限は、ポスター掲示場の数に応じて変動する複雑な計算式で算出されるため、注意が必要です。
ポスターの作成を業者に依頼する際は、事前に選挙管理委員会に上限単価を確認し、その範囲内で契約を結ぶようにしましょう。
選挙運動用ビラの作成費用
有権者に政策を直接訴えるための選挙運動用ビラの作成費用も、公費負担の対象です。
ただし、頒布できるビラは、選挙管理委員会が交付する「証紙」が貼られたものに限られます。
公費負担には、1枚あたりの単価と作成枚数に上限が設けられており、東京都知事選挙などでは、単価の上限は7円73銭に設定されています。
上限を超えた分は自己負担となるため、計画的な作成と頒布が肝心です。
選挙カーで公費負担を受けるための流れと手続き
選挙カーの費用について公費負担を受けるためには、定められた手順に沿って正確に手続きを進める必要があります。
手続きに不備があると公費負担が受けられなくなる可能性もあるため、以下4つを慎重に進めましょう。
- ・業者と有償契約を締結する
- ・選挙管理委員会へ契約届出書を提出する
- ・業者へ使用証明書などを交付する
- ・業者が自治体へ費用を請求する
詳しく見ていきましょう。
業者と有償契約を締結する
公費負担を受けるための最初のステップは、選挙カーのレンタル業者などと書面で「有償契約」を締結することです。
口約束や無償での協力は公費負担の対象外となるため、必ず契約書を作成してください。
契約書には、契約期間や契約金額、車両情報(車種や登録番号など)といった必要事項を明記します。
この契約は、立候補の届出前に行うことも可能ですが、その後の選挙管理委員会への届出は立候補後でなければ行えません。
契約内容に不明な点があれば、この段階で業者に確認し、すべて明確にしておくことが後のトラブルを防ぐことにつながります。
選挙管理委員会へ契約届出書を提出する
業者と有償契約を締結したら、次に行うのは管轄の選挙管理委員会への届出です。
締結した契約書の写しを添付した「契約届出書」を提出します。
この届出のタイミングは重要で、立候補の届出と同時に行うか、立候補後に契約した場合は契約後ただちに提出しなければなりません。
提出が遅れると、その分公費負担の対象から外れてしまう可能性があるため、迅速な対応が求められます。
この届出が受理されて、はじめて公費負担の手続きが正式にスタートします。
業者へ使用証明書などを交付する
選挙運動期間が終了したら、候補者は契約した業者に対して、契約どおりにサービスが提供されたことを証明する書類を交付する必要があります。
これが「使用証明書」や「作成証明書」と呼ばれるものです。
たとえば、選挙カーをレンタルした場合、契約期間中に間違いなくその車両を使用したことを証明するために、候補者が署名・捺印した使用証明書を業者に渡します。
この証明書は、後に業者が自治体へ費用を請求する際に必要となる書類です。
選挙戦が終わった安堵感から後回しにしがちですが、業者への支払いをスムーズに進めるためにも、速やかに対応するよう心がけましょう。
業者が自治体へ費用を請求する
すべての手続きの最終段階は、契約業者から自治体への費用請求です。
業者は、候補者から受け取った使用証明書などを添付した請求書を、市役所や町役場などの担当部署に提出します。
請求内容に不備がなければ、自治体から業者の指定口座へ公費負担分の金額が振り込まれます。
ただしこの支払いは、選挙後に対象候補者の得票数が供託物没収点を上回ったことが確定してから行われるものです。
そのため、入金までには一定の時間がかかります。
選挙カーの公費対応プランで確認すべき5つのポイント
選挙カーの公費対応プランを契約する際には、料金だけでなくサービスの内容を細かく確認することが肝心です。
ここでは、公費対応プランを選ぶ際にとくに確認すべき5つをあげます。
- ・音響設備やマイクの品質は問題ないか
- ・看板の製作やデザインまで任せられるか
- ・車両の配車や引き取りサービスがあるか
- ・面倒な申請書類の作成を代行してもらえるか
- ・万が一の事故に備えた保険・補償があるか
それぞれ見ていきましょう。
音響設備やマイクの品質は問題ないか
選挙カーの役割は、候補者の声や政策を有権者に広く届けることです。
そのため、音響設備の品質は重要です。
スピーカーの性能が低いと、音声が割れて聞き取りにくくなり、有権者にストレスを与えかねません。
クリアで遠くまで届く音質のスピーカーであれば、候補者のメッセージを効果的に伝えられます。
マイクの性能も大事です。
長時間使用しても疲れにくいハンドマイクや、身振り手振りを交えて演説できるワイヤレスマイクなど、演説スタイルに合ったものを選べるか確認しましょう。
看板の製作やデザインまで任せられるか
選挙カーの看板は、候補者の顔や名前を覚えてもらうための「走る広告塔」です。
そのため、看板のデザインは有権者の投票行動に大きく影響します。
業者を選ぶ際には、単に車両を貸し出すだけでなく、看板の製作やデザインまで一貫して任せられるかを確認するのがおすすめです。
とくに母体が印刷会社であるなど、デザインの専門知識が豊富な業者は頼りになります。
候補者のイメージや政策に合った、有権者の目を引く効果的なデザインを提案してくれるでしょう。
車両の配車や引き取りサービスがあるか
選挙期間中は、候補者もスタッフも多忙を極めます。
そのような中で、選挙カーを業者まで受け取りに行ったり、返却しに行ったりするのは大きな負担となります。
そのため、指定した場所まで車両を届けてくれる「配車サービス」や、選挙終了後に回収に来てくれる「引き取りサービス」があるかを確認することが大切です。
選挙事務所や自宅など、希望の場所まで配車・引き取りを行ってくれる業者を選べば、時間を有効に活用し、選挙運動そのものに集中できます。
面倒な申請書類の作成を代行してもらえるか
公費負担制度を利用するためには、選挙管理委員会への届出や、選挙後の請求手続きなど、多くの書類作成が必要です。
これらの書類に不備があると、公費負担が受けられなくなる可能性もあり、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
そのため、業者を選ぶ際には、申請書類の作成を代行してくれるサービスがあるかを確認しましょう。
経験豊富な業者であれば、公費負担に関する手続きにも精通しているため、正確かつスムーズに書類作成を進めてくれます。
万が一の事故に備えた保険・補償があるか
選挙運動期間中は、慣れない車両を長時間運転することも多く、交通事故のリスクは常に伴います。
万が一、事故を起こしてしまった場合、対応に追われて選挙運動が滞ってしまう事態は避けなければなりません。
そこで重要なのが、レンタルする選挙カーに付帯している保険や補償の内容です。
契約前には、対人・対物賠償の補償額は十分か、車両保険や搭乗者傷害保険は付いているかなど、詳細を必ず確認しましょう。
充実した保険・補償制度が整っている業者を選ぶことは、選挙戦を安心して戦い抜くためのリスク管理となります。
選挙カー公費対応プランを提供している業者の選び方
公費対応プランを提供している業者は数多くあり、どこを選べばよいか迷うかもしれません。
ここでは、信頼できる業者を選ぶためのポイント4つを紹介します。
- ・セット割引でお得にレンタルできるか
- ・印刷会社などデザインに強いか
- ・看板の着脱が簡単にできる車両か
- ・過去の選挙での貸出実績があるか
詳しく見ていきましょう。
セット割引でお得にレンタルできるか
選挙運動には選挙カーだけでなく、ポスターやビラ、はがきといった印刷物も不可欠です。
そこで注目したいのが、選挙カーのレンタルとポスターなどの印刷物をセットで注文すると適用される「セット割引」です。
たとえば、選挙カーと掲示板用ポスターを同時に発注することで、レンタル料金が大幅に割引されるケースがあります。
これにより、選挙運動全体の費用を効率的に抑えることが可能です。
業者を選ぶ際には、このようなセット割引があるかを確認し、総費用を比較検討することをおすすめします。
印刷会社などデザインに強いか
選挙カーの看板やポスターのデザインは、有権者に与える第一印象を決定づける大切なものです。
候補者の人柄や政策を的確に伝え、記憶に残るデザインでなければ、数多くの候補者の中に埋もれてしまいます。
そのため、業者を選ぶ際には、デザイン能力の高さも重視すべきです。
とくに、母体が印刷会社である業者はデザインのノウハウが豊富で、有権者の視点に立った効果的なデザインを期待できます。
選挙カーの看板とポスター、ビラなどのデザインに統一感を持たせることで、候補者のブランドイメージを確立しやすくなります。
看板の着脱が簡単にできる車両か
選挙運動期間中、選挙カーの看板は常に掲示しておくわけではありません。
この看板の着脱作業が複雑で手間がかかるものだと、スタッフの大きな負担となります。
たとえば、W1N選挙カーではスナップ錠などで固定し、女性1人でも簡単に看板の着脱ができるように工夫した車両をご用意しています。
こうした車両を選べば作業時間を短縮でき、その分の時間をほかの選挙運動に充てられるでしょう。
契約前に、看板の着脱方法について業者に確認することをおすすめします。
過去の選挙での貸出実績があるか
選挙運動には、公職選挙法をはじめとするさまざまな法律やルールがかかわってきます。
そのため、選挙カーのレンタル業者は、選挙特有の事情に精通している必要があります。
信頼できる業者か判断するうえで、過去の選挙における貸出実績は、安心につながる情報源です。
国政選挙から地方選挙まで、さまざまな種類の選挙での実績が豊富な業者であれば、公費負担の手続きや法律上の注意点についても不安なく相談できます。
まとめ:選挙カーの公費対応プランを賢く活用し選挙戦を有利に
選挙カーの公費対応プランを最大限活用するには、制度を理解したうえで、信頼できる業者選びが欠かせません。
W1N選挙カーでは、選挙に必要なものが全部コミコミで87,000円(税込)から提供しています。
レンタカーから音響設備、看板製作やLED照明、高音質マイクまでセットになっています。
さらに掲示板ポスターを同時発注すると5万円~10万円の値引きもあり、選挙費用を大幅に削減可能です。
印刷会社が母体のため、看板デザインからポスター、ビラまで統一感のあるデザインで有権者へアピールできます。
書類作成や申請手続きの代行、スナップ錠による簡単な看板着脱など、候補者様の負担を軽減するサービスも充実しています。
ぜひW1N選挙カーで、効率的な選挙戦を展開してください。

浅田 孝
アサダ印刷株式会社 代表取締役
W1N選挙カー 代表
1968年生まれ
累計400を超える選挙活動に従事、選挙カー貸出とともに候補者の寄り添い、共に当選を目指す。
モットーは、問い合わせメールに最短で返信(休日関係なく)依頼事は、経験なくても断らず全力で対応する。
常に、候補者目線で考え行動する。
選挙のプロであり、印刷のプロ。