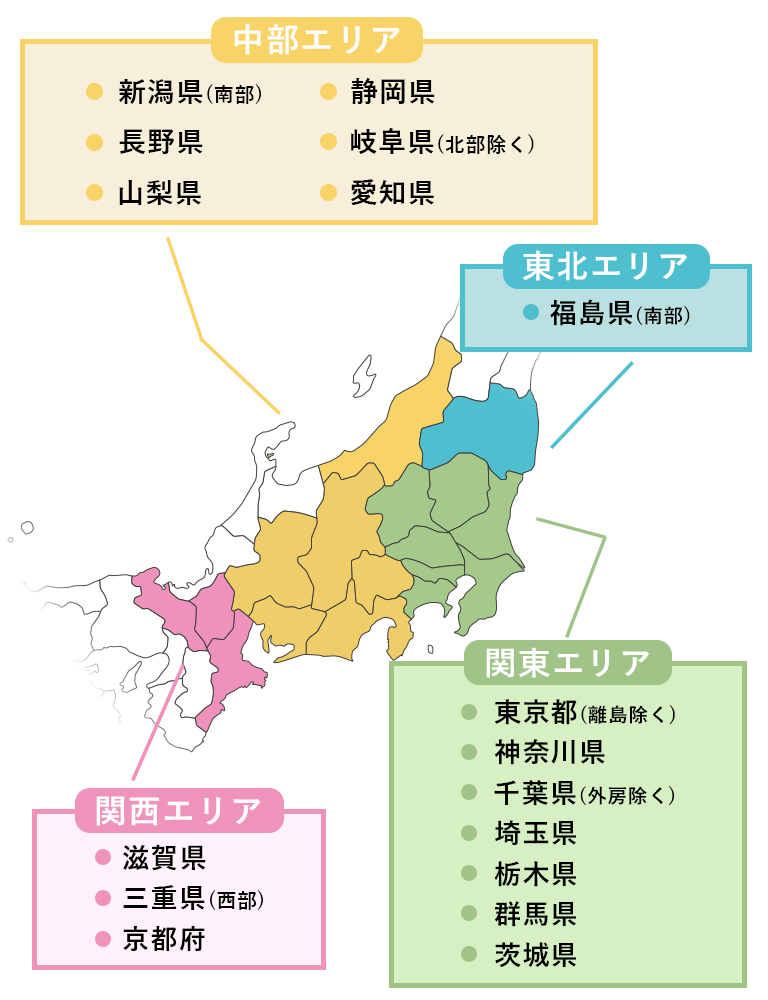選挙への出馬を検討する際、選挙運動にかかる多額の費用、とくに選挙カーの経費は大きな課題です。
しかし、候補者の経済的な負担を軽減するための「公費負担制度」があることをご存知でしょうか。
本記事では、選挙カーに関する公費負担制度の仕組みや、運転手の日当・雇用ルール、対象となる費用と上限額などを解説します。
ぜひ参考にして、公費負担制度を最大限に活用してください。
選挙カーの公費負担制度とは
選挙運動には多額の費用がかかりますが、候補者の経済的な負担を軽減するために「公費負担制度」が設けられています。
選挙運動費用の一部を国や地方公共団体が負担するもので、選挙カーの利用も対象です。
この制度について、以下3つを解説します。
- ・制度の目的
- ・公費負担の仕組み
- ・対象となる選挙
これらの基本を理解することが、制度活用の第一歩です。
制度の目的
公費負担制度のおもな目的は、候補者間の選挙運動における機会均等を確保し、「お金のかからない選挙」を実現することです。
もし選挙費用がすべて自己負担であれば、資金力のある候補者が有利になり、資産の多寡が選挙結果を左右しかねません。
このような事態を防ぎ、候補者の資質や政策本位で選挙が行われるよう、費用の一部を公費で負担する仕組みが作られました。
新人候補者にとっては、資金面のハンディキャップを乗り越え、公平な条件で選挙戦を戦うための貴重な権利といえるでしょう。
▼選挙費用について詳しく知りたい方はこちら
選挙費用はすべて自己負担?項目別の内訳や費用を抑えるための対策も紹介
公費負担の仕組み
公費負担制度の大きな特徴は、費用が候補者に直接現金で支給されるわけではない点です。
代わりに、候補者が契約した事業者(レンタカー会社やガソリンスタンドなど)に対し、選挙後に自治体から直接費用が支払われる仕組みになっています。
また、候補者が選挙期間中に多額の費用を一時的に立て替える必要がなくなるため、手持ち資金が少なくても選挙運動を展開できるのもメリットです。
ただし、事業者は選挙後に自治体へ請求手続きを行うため、入金までに一定の期間を要します。
そのため、この仕組みに対応してくれる事業者と契約する必要がある点を覚えておきましょう。
▼選挙カーの公費対応プランについて詳しく知りたい方はこちら
選挙カーの公費対応プランとは?確認すべき4つのポイントについても解説
対象となる選挙
公費負担制度は、以下のように多くの選挙で適用されています。
- 衆議院議員選挙や参議院議員選挙
- 都道府県知事選挙や都道府県議会議員選挙
- 市区町村長選挙や市区町村議会議員選挙
公費負担制度は、公職選挙法が適用される多くの選挙で利用できます。
具体的な費用の種類や上限額は、選挙の種類や、地方選挙の場合は各自治体が制定する条例によって異なる場合があります。
選挙カーの運転手の日当や公費負担に関するルールについて
選挙カーは公費負担制度の中でも中心的な項目ですが、利用には詳細なルールが定められています。
ここでは、選挙カーの公費負担について、以下5つを説明します。
- ・ハイヤー契約とその他の契約から選ぶ
- ・それぞれの上限額を把握する
- ・運転手の雇用ルールを遵守する
- ・燃料代の請求ルールを把握する
- ・対象外となる費用を認識する
これらの具体的なルールを学び、制度を適切に活用しましょう。
ハイヤー契約とその他の契約から選ぶ
選挙カーの公費負担を利用する際、契約方法は「ハイヤー契約」と「その他の契約(個別契約)」の2種類からどちらか一方を選択します。
選挙運動用自動車の使用に関して、同一の日に両方を締結した場合、公費負担の対象となるのは候補者が指定するどちらか一方の契約のみです。
ハイヤー契約(一般運送契約)は、道路運送法に定める一般乗用旅客自動車運送事業者と結ぶ契約で、車両や燃料、運転手を一括で手配する方式です。
一方、個別契約は「車両のレンタル」「燃料の供給」「運転手の雇用」をそれぞれ別の事業者と契約します。
コストを抑えられる可能性がありますが、契約や請求の手続きが煩雑になります。
選挙事務所の体制やかけられる手間などを考慮し、自身の選挙戦略に合った方式を選びましょう。
それぞれの上限額を把握する
選挙カーの公費負担には、契約方法ごとに上限額が定められています。
以下は、東京都知事選挙・都議会議員補欠選挙の例です。
|
契約の種類 |
項目 |
公費負担の上限額 |
備考 |
|
ハイヤー契約 |
車両・燃料・運転手の一括契約 |
1日あたり64,500円 |
車両、燃料、運転手の費用がすべて含まれる |
|
個別契約 |
自動車のレンタル料 |
1日あたり16,100円 |
車両本体の借入れ費用のみが対象 |
|
燃料代 |
7,700円 × 選挙運動日数 |
期間中の総額で管理される |
|
|
運転手の報酬 |
1日あたり12,500円 |
運転業務への対価として支払われる |
詳しく見ていきましょう。
ハイヤー契約
車両や燃料、運転手を一括で契約する方式です。
この契約方法を選択した場合、公費負担の1日あたりの上限額は64,500円に設定されているのが一般的です。
この金額には、車両のレンタル料やガソリン代、運転手の報酬がすべて含まれています。
選挙運動期間中の合計上限額は、この日額に選挙運動日数を乗じて算出されます。
手続きが簡便で、管理しやすい点がメリットです。
しかし、個別契約よりも費用が高くなる傾向があるため、事前に複数の事業者から見積もりを取ることをおすすめします。
自動車のレンタル料
個別契約で選挙カーを用意する場合、車両本体のレンタル料も公費負担の対象となります。
この場合の1日あたりの上限額は、多くの自治体で16,100円に設定されています。
ただし、公費負担の対象となるのは、あくまで車両本体の基本的なレンタル料金のみです。
そのため、複数のレンタカー会社を比較検討し、計画的に契約を進めましょう。
▼選挙カーレンタル時の故障対応について詳しく知りたい方はこちら
選挙カーレンタル時の故障対応とは?トラブルの種類や対応時の流れを解説
燃料代
個別契約の場合、選挙カーに供給した燃料代も公費負担の対象です。
燃料代の上限は、1日あたりの上限額(東京都知事選挙などの例:7,700円)に選挙運動期間の日数を乗じた総額で管理されます。
この総額の範囲内であれば、1日ごとの給油量に制限はありません。
活動量が多い日に多く給油し、少ない日は給油しないといった柔軟な運用が可能です。
ただし、対象となるのは届け出た選挙カー1台分のみで、随行車などの燃料代は含まれません。
運転手の報酬
選挙カーの運転手を個別に雇用した場合の報酬も、公費負担の対象となります。
1日あたりの上限額は12,500円が一般的です。
この報酬は、あくまで運転業務に従事したことに対する対価となります。
公費負担の対象となるのは、1日につき1名分のみです。
午前と午後で運転手を交代した場合でも、報酬を支払えるのは事前に届け出たどちらか1人だけとなります。
運転手の雇用ルールを遵守する
運転手の雇用は、公費負担制度の中でもとくに厳格なルールが定められています。
まず、公費負担の対象となるのは、候補者と運転手個人が直接締結した雇用契約のみです。
もっとも注意すべきは、親族を運転手として雇用する場合です。
候補者と生計を同一にする親族(配偶者や同居の親子など)に運転を依頼しても、原則としてその報酬は公費負担の対象外となります。
ただし、その親族が運送業などを職業として営んでいる場合は例外的に対象となります。
燃料代の請求ルールを把握する
個別契約で燃料代の公費負担を申請する場合、請求手続きには厳密なルールがあります。
もっとも重要なのは、給油した際の「給油伝票の写し」をすべて保管しておくことです。
この伝票には、給油日と車両の登録番号、給油量や金額が記載されている必要があります。
これらの情報が記載された給油伝票の写しがない場合、請求は認められません。
選挙期間中は、給油のたびに必要事項が記載されたレシートを受け取り、紛失しないよう専用のファイルなどで一括管理する体制を整えることが不可欠です。
対象外となる費用を認識する
選挙カーに関わる費用のうち、公費負担の対象外となるものを正しく認識しておくことは、予算オーバーを防ぐうえで大切です。
公費負担の対象は、あくまで「選挙運動用自動車の使用」そのもの、つまり車両の基本的なレンタル料金や燃料、運転手の報酬に限られます。
そのため、選挙カーに付きものである看板やサイン、スピーカーやアンプといった拡声装置などの費用は、原則として公費負担の対象外です。
これらの費用は、選挙運動に必要な経費として別途予算を確保しておく必要があります。
選挙カー以外も公費負担の対象になる選挙運動費用
公費負担制度は選挙カーだけでなく、有権者に政策を伝えるための主要な広報物も対象です。
具体的には、「選挙運動用ポスター」と「選挙運動用ビラ」の作成費用が公費で賄われます。
ポスターとビラについては、作成できる枚数や単価に上限が定められており、その範囲内で実費が負担されます。
まとめ:選挙カー公費負担制度を最大限活用するために
選挙カーの公費負担制度は、選挙運動の費用を抑えるために不可欠ですが、手続きが煩雑な側面もあります。
W1N選挙カーでは、車両レンタルはもちろん、看板製作や高音質マイクといった音響設備まですべてコミコミでご提供します。
母体が印刷会社のため、選挙ポスターとのデザイン統一も可能です。
面倒な公費負担の申請書類作成も代行しますので、候補者様は選挙運動に集中できます。
まずはお気軽に、お問い合わせください。

浅田 孝
アサダ印刷株式会社 代表取締役
W1N選挙カー 代表
1968年生まれ
累計400を超える選挙活動に従事、選挙カー貸出とともに候補者の寄り添い、共に当選を目指す。
モットーは、問い合わせメールに最短で返信(休日関係なく)依頼事は、経験なくても断らず全力で対応する。
常に、候補者目線で考え行動する。
選挙のプロであり、印刷のプロ。